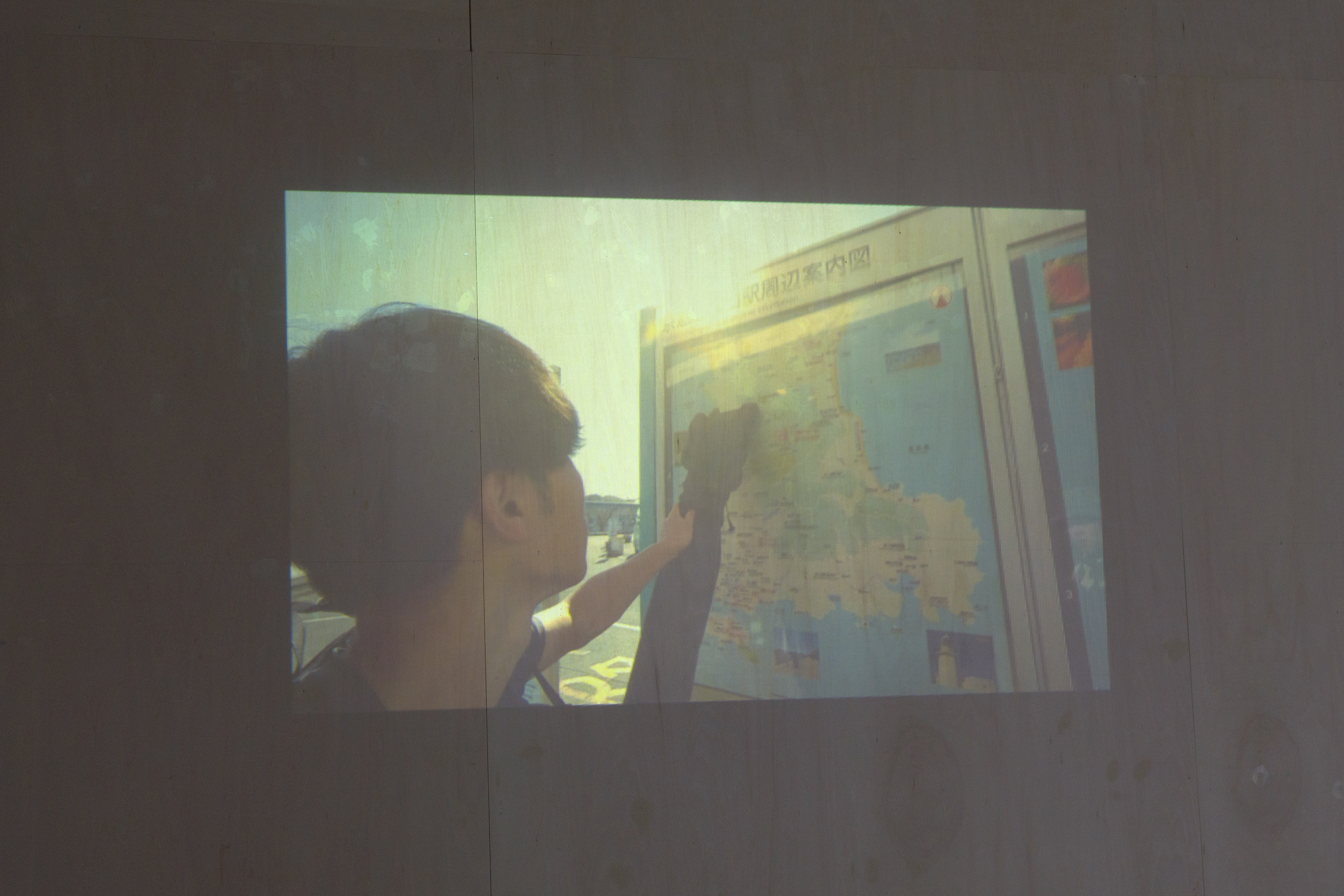



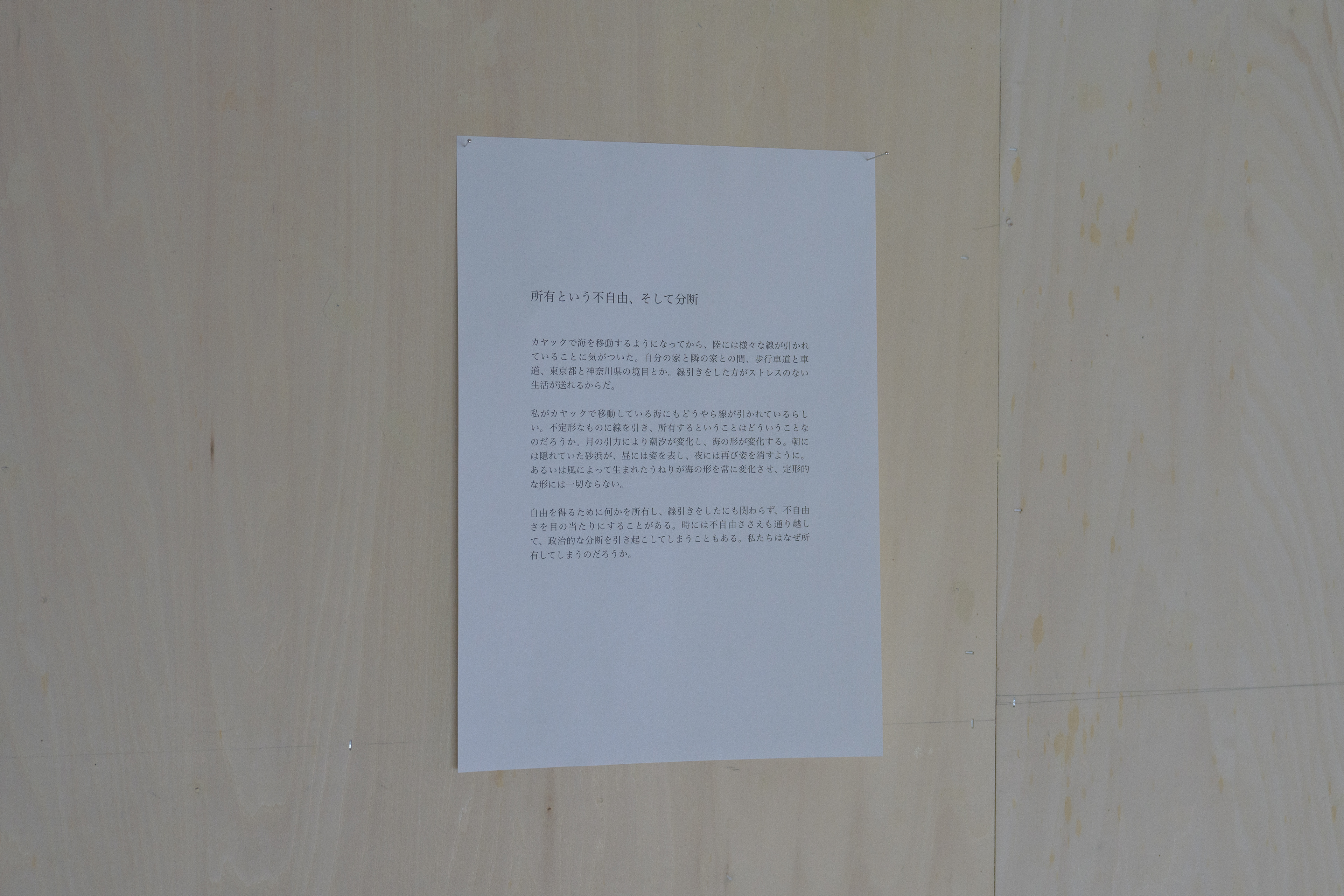
At Sea / 海にて
2024, Installation: double-channel video, 3 light boxes with colour transparencies
Cooperation: Kazuya Matsuhashi
DM: Mei Ohashi
A lack of freedom named ownership and division
Since I began crossing the sea by kayak, I have become aware of various boundaries on land—those between my house and others, between pavement and roadway, or between Tokyo and Kanagawa prefecture. These lines simplify our lives and reduce conflict.
Yet boundaries also seem to exist on the sea where I paddle. What does it mean to draw lines on something indefinite and claim ownership? The moon’s gravitational pull affects the tides, reshaping the sea. Hidden beaches emerge in the morning only to disappear by night. The wind-driven swells constantly alter the sea’s form, emphasising its fluidity.
In our pursuit of freedom, we establish ownership and boundaries, yet this pursuit can paradoxically lead to a lack of freedom and even political divides. Why must we possess things instead of letting them simply be?
所有という不自由、そして分断
カヤックで海を移動するようになってから、陸にはさまざまな線が引かれていることに気がついた。自分の家と隣の家との間、歩行者道と車道、東京都と神奈川県の境目とか。線引きをした方がストレスのない生活が送れるからだ。
私がカヤックで移動している海にもどうやら線が引かれているらしい。不定形なものに線を引き、所有するということはどういうことなのだろうか。月の引力により潮汐が変化し、海の形が変化する。朝には隠れていた砂浜が、昼には姿を表し、夜には再び姿を消すように。あるいは風によって生まれたうねりが海の形を常に変化させ、定型的な形には一切ならない。
自由を得るために何かを所有し、線引きをしたにも関わらず、不自由さを目の当たりにすることがある。時には不自由ささえも通り越して、政治的な分断を引き起こしてしまうこともある。私たちはなぜ所有してしまうのだろうか。
批評、助言、メモとか
ロック:資本主義社会においては「お金」を介することで「自由」を得ることが可能になる。
ルソー: 共同体の規則に自分自身の意思で従うことで「自由」を得られる。
カヤックを漕ぐこと -> 妨害されるものがないからどこまでも行ける。
看板を立てようとすること -> 形がないから固定することができない。
線を引こうとすること -> 波があるから、固定することができないし形が不安定。
T田さんから
電話番号を変えてパフォーマンスをすることで、実際に売っている人がいることを示唆できる。
売地の看板をずっと沈めていて、固定できないことに苦しむ水中映像。
ロープをコケとかが着くまで放置したものを展示すると、ランドアート的な新たな意味が含まれるようになる。
M陰さんから
ドキュメンテーションの状態をどのように追体験させるかが今後の課題
M橋くんとの会話だったと思う。
抽象的な映像(潘さんのような)になるか、固有名詞とか具体性のあるものを組み込んで賑やか?なものにするか。
最初の記録映像は他の作品とは別個のものだから、モニターがベストだった。
音質を考える。スピーカーを噛ませた方が良かった。
斎藤先生から
物量に訴えていないことが、現代的らしい。
インスタレーションは一過性のものであり、所有することへの抵抗から始まった部分もある。
モノを下に置くと、質量が減る。
今では輸入とかが進んでいるから、そんなに珍しいものでもない。だけど、展示の仕方だったりを工夫すれば流れ着いてきたことがわかる。 (異なる作品について。)
M橋くんから
ステートメントではなくて、3歳児でも食い付くような映像から入るといい。
セオリー通りではなくて、その人がどうしても入れたかったんだなという要素があると作家が見えてくる気がする。
by Uらさん
ラズパイで動画再生できる機械が作れるらしい。
11/7
撮影者が被写体として入っていてもいいのでは、声があるし。どう見せるかによって映像の編集方法が変わってくる。
10/24
カヤックを作品に取り入れてみる。
展示する際に気を付けることは、カヤック売り場みたいにならないこと、カヤック少年の旅みたいな作品にならないこと、なぜカヤックだったのかということを深掘りして、作品に脇役として組み込むこと。
10/17
海、山、川、土地の個人所有が増えていった時に自由に使える場所がなくなることに対する「不自由」さを表現するために、結果だけではなく過程を見せる。
つまり、ここは誰々の土地で、ここは誰々の川で、ここは誰々の山でというようなものを帰納法で提示していった上で、自分自身(作家)が海を所有しようとするパフォーマンスを見せる。
10/10 (この頃は言葉の看板を制作していた。)
横位置の水中写真(1枚)を展示して、スポットライトで照らす。
言葉を足してみる(看板は遠近感を考えてサイズを選ぶこと)
Make Sites into Capital
Find Sites to Make Profit
Find Sites to …
Acquire Land to Generate Capital
Transform Land into Capital
言葉を足したことでより説明的になった。説明的な作品、つまりコンセプチャル・アートにするにはもっと頭で考えていることを明確に言葉にしていく必要がある。その上でヴィジュアルを面白くすれば、作品として成立する。
動画が静止画的に撮影されているから、物体とは整合性があるけれど、吊るしている言葉とはあまり合っていない。言葉を物質化してもいいし、映像を静止画にして全体との整合性を調整してもいい。
9/19
要素を足すこと。スクリーンが大きくなるほど、映像もそれに耐えられるだけの要素がなければならない。
会話や朗読(音声)を足してみたり、映像の中で他の登場人物がでてきてもいいし。
9/5
海の音が繊細ではないから、それを別で録音して被せた方がいいんじゃないか。
ストイックなものとは真逆に撮影に行くまでの過程を全て撮影するのはどうか。
要素を削るとストイックな作品になり、要素を増やすと「説明的」な作品になる。
7/18
広角から望遠(手元)はあるけど、行為者が映っている映像が欲しいから中間のもあるといい。
広角から標準、望遠という順で構成すると、説明的かもしれないけど観客は何をやっているかが分かる。
出来上がりをイメージしながら、作っていくこと。
手作業が見えないような作品は、素材、展示方法などで作品として成り立つかが決まる。
夏休みの宿題
3チャンネルの映像にする。
広角、標準、望遠で映像を分けて、それぞれの映像を一つの出力から操作できるようにする。
6/20
物体は自身の理想とどこかで折り合いをつける。魔法を使うことは難しい。
時間を表現するのに時計を使うことは説明的すぎる。
模型と実物は空間によって見え方が変わる。模型は模型でしかなく、実際に見た時の印象が全く異なるから、あてにしないほうがいい。
絵は写真の出現によって記録という部分が無くなり、抽象主義絵画へと変遷していった。
Robert Rauschenberg
見えない土地を売ることについて
使いたい音のイメージを考える。
6/13
汲んできた水とそこにある海水は異なる。水は形を持たないから抽象的な存在で魅力的。
説明的なものになってしまうから作品よりも言葉が先に出てきてはならない。批評は後から付いてくるもの。
コンセプトとヴィジュアルの適正な割合を知る。これは考えていても分からないから、制作しながら探っていく。
お金と水の組み合わせはどうしてもローマの泉や、お賽銭のようなものを想起させる。
レアメタル、資本、環境、人、土地、海
解説があってもなくても良いものが作品で、文化遺産として残っていないものはゴミ。
立体について
昔の彫刻は台座の上に造られていて、台座という立方体の中(絵でいう額縁)での出来事を表現している。
ヨーロッパでは木よりも石の方が安いから、大理石とかが日常的に使われていた。
Constantin Brancusi から彫刻における台座がなくなってきた。これはインスタレーションにも通づるもので、彫刻が配置されている環境自体に存在しているという意味。
Louise Bourgeois は自らの過去のトラウマをアートとして昇華している作家。
被害者側をテーマにした方が作品にしやすい。だけど、Gerhard Richter は最新のアウシュヴィッツをテーマにしたペインティングで加害者側をテーマに制作した。
Anthony Gormley, Rachel Whiteread, Tony Cregg
6/6
身近な関係性から生じた作品は共通認識が制作の助けとなる。
感覚や経験から離れると作品にすることが難しくなる。
フランジェリコの受胎告知も一点透視法になっている
サン・マルコ修道院にも最後の晩餐がある。
キリストをモチーフにした作品では手や足に穴が空いたものがある。
産業革命以前は絵の具がチューブに入っておらず、調合が大変であったため、室内で作品が制作されていた。
オランダ出身のフェルメールは光学的な視点を持っていたのではないか。
印象派は抽象画への橋渡しとなっている。
イスラム教は偶像崇拝を禁止されているが故に、装飾に凝るようになった。
Black on black のコラージュ
Mark Rotsukoの抽象作品は空間の外に出てくる意識がある。川村記念美術館に作品がある。
de Kooning, Ellesworth Kelly
額縁があることで外界とのつながりをもたらす。ないことで空間を変容させることがインスタレーションにつながった。
5/30
ロード・トリップのような動いている写真は何枚も撮っておくべき。
パンフォーカスだと記録写真のようになる。ピントの位置をずらすと物語性が生まれる。
アテナイの学堂
手前に対象物があって、奥に虚構が広がっているのが西洋式 -> 壁の奥に異なる世界が広がっていること。
対して日本画は逆パースが採用されている。逆パースを伸ばし続けると、辻褄があわなくなるため、雲や障子で隠している。
絵巻は基本的に上から見るから、逆パースが合う。
リカちゃんハウスと源氏絵巻は同じ。日本で制作される作品が小さかったのは、小さい範囲でも楽しめるようにすることが原因だったのではないか。
日本において書画は芸術の一つとされているが、西洋ではカリグラフィーとして認識され、デザインの範疇になる。
日本ではアニミズムの精神(物質に精神が宿る)考えが主流であるため、手仕事の制作物は芸術品として扱われることが多い。これが理由であらゆる職人の地位が日本では高い。
例えば、韓国は儒教の国であるため、物作りに対する評価が低く、西洋と同様に哲学を重んじている。
アンディ・ウォーホールがマリリン・モンローをモティーフに使用したのも誰もが知っている前提としての記号としてだった。
Jasper Jonesの時代には国旗が芸術として扱われることはなかった。彼は絵画の物体化を行った。
Conceptual Artは感情や感覚のような曖昧なものを排除したもの。誰もやったことのない作品を制作しており、そのコンセプトを説明する必要がある。
コンセプトとヴィジュアルの両方が揃っているものが残っているように思う -> 斎藤先生
・斎藤義重 -> コラージュの習作の参考とする。
・Rebecca Horn
・田中敦子 -> 具体の人
・高松次郎
5/23
Mario Merz, Fiona Tan, Pipilotti Rist,
売地の作品は写真と映像にした方が良さそう。ゲリラ的に様々な場所に設置するのもありだが、機動性に欠けるのと、イタズラっぽく見えないから危ない。
土地の所有を無効化することをテーマとすると、ユートピア的な考えになる。つまり、共有、共存みたいな思想で新鮮味がなくて詰まらない。
消費社会への皮肉的な視線をテーマにした方がよい。例えば、誰にも所有されていない「海」、「宇宙空間」に看板を浮かべてドローンで映像化する。場所の消費が最後に行き着く。
最近注目されている作家に目を向けるのではなく、何十年にも渡って残っている作品を制作しているアーティストを参考にするべき。そうすれば、いつの時代でも通用する作品が生み出せるはず。
5/16
プライベートはドキュメント写真で問題点となるのは人の痕跡を残すか、残さないかで印象が変わる。ドキュメントは基本的に人の痕跡で成り立つ。
テーマ自体はやりながら決めていくことの方がいい。最初からテーマを設定してしまうと、そのテーマから溢れているものが拾えなくなるから。
売地の作品は置く場所によって意味が変わる。室内に置いている時は不自然だからこその面白さがある。一方で野外に置くとどう見えるかは分からない本物に見えた方がいいのか、偽物に見えた方がいいのか。それも何を伝えたいかによって変わってくる。
奥多摩の作品は今撮影しているものは過去のものでお祭りになると現在進行形になってくる。資料では手に入らない情報が必要。
テーマが「土地性」だと散漫としているから何が言いたいのかが分からない。一つの物語があるといいのではないか。
ヨーロッパでは宗教、哲学、芸術が三位一体となっている。
Relational Art
・Rirkrit Tiravanija
・Francis Alys
・Tsuyoshi Ozawa
Interactive Art
・Felix Gonzalez Torres
Others
・Sara Sze
・Tom Friedman
・Damian Hirst
・Pipilotti Rist
・Uta Barth
・野口里佳
5/9
写真を撮ってる時に時間を追う感覚とパフォーマンスアートは似ている。
映像には音声が欲しい。
音によってオブジェクトが持っていた意味が変わるから、ヴィジュアルが重視されているものと音声が一緒の作品を制作する際は注意しなければならない。
縦方向に流れる映像があってもいい。
ドキュメントなのに、深い部分まで入り込んでいない感じがする。言葉で縛って、それに即したものしか写していないのが勿体無い。
写真は現実よりも美しくなければ撮る意味がない。
Alfredo Jaar
JR(Jean Rune)